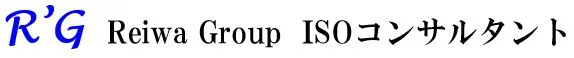著しい環境側面にどう対応する?~目標設定・管理・改善の進め方~

前回の記事では、ISO14001における「環境側面」の考え方や、著しい環境側面の特定方法についてご紹介しました。
今回は、その続編として「特定された“著しい環境側面”にどう対応するか?」に焦点を当てて解説します。
これは、単にISOの要求を満たすだけでなく、企業のリスク回避や信頼性向上にもつながる大切な取り組みです。
◆ 著しい環境側面とは「放っておけない環境リスク」
ISO14001では、環境影響のうち、特に重要なものを「著しい環境側面」と定義しています。
これには、法規制の対象になっているもの、地域や顧客の関心が高いもの、事故や緊急時に重大な影響を与える可能性があるものなどが含まれます。
このような環境側面を特定するだけでなく、「計画的に管理・改善していくこと」が、6.1.4や6.2、9.1.1の中で求められています。
◆ 4つの柱で進める管理プロセス
著しい環境側面への対応は、以下の4つのステップに分けて考えるとわかりやすくなります。
① 目標の設定(ISO14001:6.2項)
まずは、著しい環境側面に対してどんな結果を目指すかを明確にします。これは「環境目標」と呼ばれます。
例:
- 有機溶剤の排出量を前年比10%削減する
- 電力使用量を年1%削減する
- 廃液の発生件数ゼロを目指す
目標は、定量的に表現し、達成時期や責任者も明確にすると、実行しやすくなります。
② 管理策の実施
目標を達成するための手段=「管理策」を講じる必要があります。内容は、工程の改善や設備の導入、作業手順の見直しなど、具体的な対策です。
例:
- 換気設備の増設によるVOC排出の低減
- 節電プログラムによる使用電力の管理
- 緊急時の対応マニュアルや模擬訓練の実施
通常の業務だけでなく、緊急時(火災・漏洩など)への対応計画も含めることが重要です。
③ モニタリングと測定(ISO14001:9.1.1項)
設定した目標に対して、現在どこまで進んでいるのかを測るために、モニタリングと記録が欠かせません。
ポイント:
- 測定の頻度、方法、責任者を明確にする
- 測定結果を記録として残す
- 達成度を定期的に確認する
「数値で見える化」することで、関係者全員が取り組みの効果を実感でき、次の改善にもつながります。
④ 改善のサイクル(PDCA)
ISO14001は、単発的な対応ではなく継続的な改善を重視しています。目標の達成度を分析し、必要な場合は対策を見直す。このPDCAの繰り返しが重要です。
改善につながる活動例:
- 内部監査での指摘を受けた工程を見直す
- 排出量が基準を超えた原因を調査・改善
- 目標が高すぎた/低すぎた場合の見直し
これらは、マネジメントレビュー(9.3項)でも重要な判断材料になります。
◆ 【事例紹介】製造業での著しい環境側面の対応例
以下は、金属加工工場における著しい環境側面への対応事例です:
|
環境側面 |
管理目標 |
管理策 |
測定方法 |
|
有機溶剤使用 |
年間排出量10%削減 |
封じ込め装置導入、換気強化 |
揮発量の記録測定 |
|
電力使用 |
年1%削減 |
LED照明化、機械のアイドルストップ |
電力モニターの記録 |
|
油漏れ(緊急時) |
年間ゼロ件 |
配管点検・模擬訓練の実施 |
事故報告・記録 |
このように、具体的な対応と記録を組み合わせることで、審査対応にも強くなり、現場の意識改革にもつながります。
◆ よくある課題と対策
|
よくある課題 |
解決アドバイス |
|
目標が抽象的で実行しにくい |
数値化し、達成期限と責任者を設定する |
|
モニタリングが形骸化 |
現場と一緒に測定・記録方法を再検討する |
|
記録が残っていない |
デジタル記録やチェックリストを活用 |
◆ まとめ:管理の積み重ねが信頼を生む
著しい環境側面は、「見て見ぬふり」が通用しないリスク要素です。
だからこそ、明確な目標、具体的な対策、確実な測定、地道な改善が企業の信頼と競争力につながります。
環境マネジメントは、経営に役立つ道具です。形式だけで終わらせず、実効性のある取り組みを目指しましょう。
▼ 次回のブログ予告
**「環境目標はどう事業目標とリンクさせるか?~経営視点でのISO活用術~」**を予定しています。
▼ 無料の一日診断で現状チェック
「自社の管理が正しくできているか不安…」という方へ。
【無料の一日診断】で、現状確認と改善アドバイスを行っています。
▶ 詳しくはこちら:
お気軽にお問い合わせください。

ISO(9001/14001)一日診断、認証取得のコンサルタント、現状のシステムの見直しと改善、内部監査教育や支援、ご質問などお気軽にお問合せ下さい。貴社のニーズに合う最善のご提案とサポートをご提供いたします。