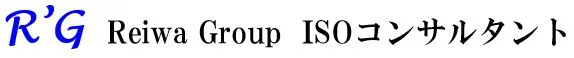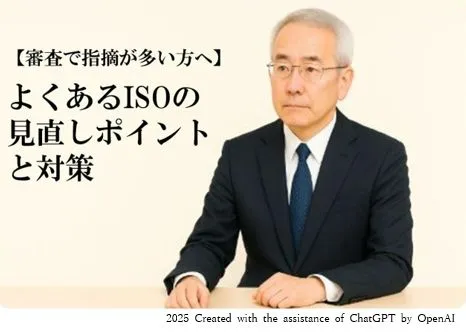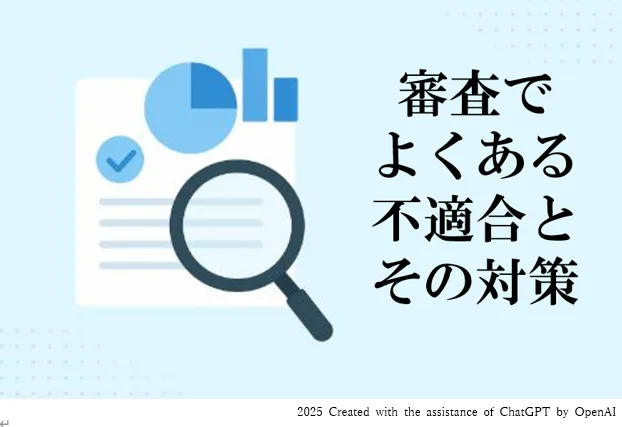監査員に伝えるべきは“手順”ではなく“意図”~ISO審査の場面で本当に問われる“考え方”と“目的達成の説明”力について~
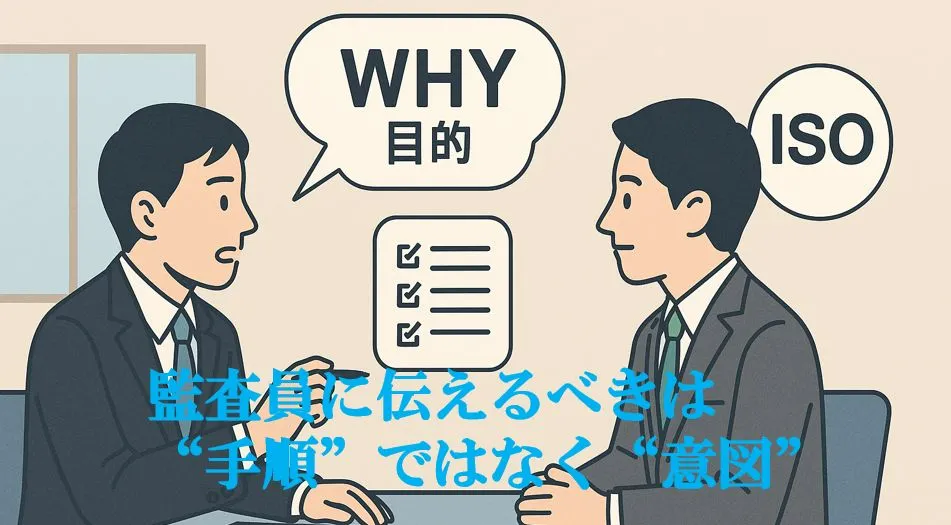
ISO審査で本当に問われるのは「手順」ではない
ISO審査の場面では、受審者が「手順」を細かく説明しようとする場面をよく見かけます。
「こういう流れで処理しています」「マニュアル通りにやっています」という説明は、確かに必要最低限の情報です。しかし、監査員が本当に知りたいのは、単なる“手順の羅列”ではありません。
監査員の関心は、その手順が どのような目的を達成するために設定されたのか、そして 実際に仕組みが意図通りに機能しているか にあります。つまり、手順よりも「意図」や「考え方」を説明できることが、審査における最大のポイントなのです。
ISO審査における監査員の視点
手順よりも意図を確認する監査の本質
ISO審査員は、組織が認証基準を満たしているかを確認しますが、その際に「チェックリスト的な手順の有無」を調べるのではなく、仕組みが合理的に設計され、目的を果たしているかを見極めようとします。
もし「報告書は作っています」「教育は計画通りにやっています」と説明しただけでは、監査員には十分に伝わりません。「その活動の狙い」と「達成しようとしている目的」が語られなければ、監査員は「形式的にやっているだけでは?」と疑問を持つのです。
ISO審査で見られる3つのポイント
監査員が注目しているのは、主に次の3点です。
- 目的が明確か:このプロセスは何を達成するためのものか。
- 手順が合理的か:意図を実現するために設計されたプロセスか。
- 成果につながっているか:単なる実施記録ではなく、改善や効果が確認できているか。
「意図」を説明することが重要な理由
手順=How、意図=Why
ISO審査での説明を「手順」に偏らせてしまうと、表面的なやり取りに終わってしまいます。手順は「How」、つまり方法論にすぎません。一方で、監査員が本当に評価したいのは「Why」──なぜその方法なのか、どんな目的を果たそうとしているのか、という部分です。
監査員に伝えるべき3つの要素
監査員に“意図”を伝える際には、次の3つを整理しておくと効果的です。
- 目的(なぜ行うのか)
例:教育訓練は「力量を確保するため」に実施している。 - 理由(なぜその方法を選んだのか)
例:OJT中心としたのは、自社に合った実務教育だから。 - 成果(どのように効果を確認しているのか)
例:教育後の評価シートや不良率の改善で効果を確認している。
これらを語れるかどうかで、監査員の印象は大きく変わります。
現場での事例:意図が伝わった説明の瞬間
事例1:教育訓練の説明方法
ある製造業の現場で、監査員が「教育訓練はどう実施していますか?」と質問しました。担当者は最初「教育計画を立てて実施しています」と答えましたが、それだけでは監査員は納得しません。
そこで担当者は続けて「作業品質を安定させるため、経験の浅い社員に対してOJTを中心に実施し、評価を通じて力量が確保されているか確認しています」と説明しました。この瞬間、監査員は「意図と効果が伝わった」と納得したのです。
事例2:不具合処理の説明方法
別の企業では、不具合が発生した際の処理について問われました。担当者は「報告書を提出しています」と答えましたが、それでは「単に書類を出しているだけ」に聞こえてしまいます。
そこで「不具合の原因を明確にし、再発防止のために改善策をチームで検討・実施しています」と説明したところ、監査員は「単なる報告ではなく改善に結びついている」と評価しました。
説明力を高めるための準備
社内教育で“意図ベース”の理解を浸透させる
社員教育の際に「手順を覚える」だけではなく、「その手順の目的は何か」を常に意識させることが重要です。マニュアルを読むときも「この項目はどの目的を達成するためにあるのか」を考える習慣をつけると、審査で自然に意図を語れるようになります。
模擬審査でWhyを問うトレーニングを実施する
模擬審査の場で「なぜ?」を繰り返し問うことで、現場担当者が意図を自分の言葉で説明できるようになります。「手順通りです」だけでは不十分で、「なぜその手順なのか」を語れるようにすることが狙いです。
経営層・現場リーダーが共に説明できる体制をつくる
ISOの意図を説明できるのは現場担当者だけではありません。経営層が「ISOを経営改善にどう活かしているか」を語れることも重要です。トップから現場まで一貫して「目的を語れる」状態を作ることで、審査員からの信頼性が高まります。
よくある誤解と失敗例
手順書をそのまま読み上げてしまう
監査員は「マニュアルを読む」ために来ているわけではありません。自分の言葉で説明できないと「理解していない」と見なされる恐れがあります。
「はい/いいえ」でしか答えられない
監査員からの質問に対して「はい」「やっています」だけでは説得力がありません。「何のためにやっているのか」を添えることで回答に厚みが出ます。
監査員の質問を“突っ込み”と誤解してしまう
監査員は揚げ足を取るのではなく、意図を確認しているのです。質問の背景を理解すれば、前向きに説明できるようになります。
まとめ:ISO審査は「意図」を語れるかどうかで評価が変わる
ISO審査においては、手順の説明だけでは不十分です。監査員が知りたいのは「なぜその手順を選び、どのような成果を上げているのか」という意図と考え方です。
- 手順=How(方法)
- 意図=Why(理由・目的)
このWhyを語れることが、審査で高く評価されるポイントになります。
ISOは単なる認証制度ではなく、組織改善の仕組みです。意図を説明する力を養うことで、審査を自信を持って迎えられるだけでなく、組織全体の成長にもつながります。
関連サービスのご案内
当社では「意図を語れるISO」を実現するために、次の支援を提供しています。
- 無料の一日診断:自社の仕組みが“意図を説明できる状態”になっているかを確認できます。
- 模擬審査・教育支援:監査員の視点から「意図を説明するトレーニング」を実施し、現場力を強化します。
ISO審査で“自信を持って意図を語れる組織”を一緒に目指しましょう。
\ ISOについてこんなお悩みありませんか? /
- ISO認証を取りたいが、何から始めればいいか分からない
- 今のISOが形骸化してしまっていないか不安
- もっと現場に役立つ、シンプルで使いやすい仕組みにしたい
そんなときは、ISOの経験豊富な現役主任審査員が無料でご相談に応じます。
初回相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
【ご相談内容に応じて、通常、1営業日以内を目安に返信いたします】
👉 ご質問・ご相談は、下記のフォームよりどうぞ。
お気軽にお問い合わせください。

ISO(9001/14001)一日診断、認証取得のコンサルタント、現状のシステムの見直しと改善、内部監査教育や支援、ご質問などお気軽にお問合せ下さい。貴社のニーズに合う最善のご提案とサポートをご提供いたします。