ISO要求事項追加の“気候変動”への対応について
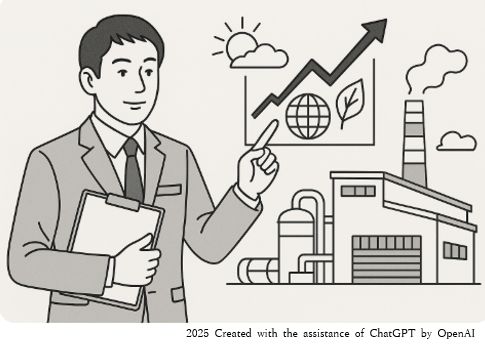
2024年2月に発行された共通附属書SLの改訂で、「気候変動」が新たに考慮すべき外部課題のひとつとして明示されましたが、どのように対応すれば良いのでしょうか?製缶業を例に、具体的な対応の考え方について解説します。
4.1 組織及びその状況の理解
(外部課題としての気候変動の影響を把握する)
製缶業を取り巻く外部環境として、気候変動が与える影響を理解することが求められます。たとえば、夏場の猛暑が作業員の体調に影響を与え、生産効率が低下する可能性があります。また、異常気象により、鋼材などの材料納入が遅れるリスクも考えられます。
こうした気候変動由来のリスクを「外部の課題」として把握し、マネジメントシステムに反映することが重要です。
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
(顧客や行政の「気候変動対応」への関心を把握する)
顧客や地域社会、行政などの利害関係者が、脱炭素や省エネに対する期待を持っているケースが増えています。例えば、取引先から「環境に配慮した製造工程であること」の証明を求められることや、自治体から省エネ診断を受ける機会があるなど、気候変動への対応が利害関係者のニーズになっていることを認識し、それを品質マネジメントに反映させます。
6.1 リスク及び機会への取組み
(気候変動に関連するリスクや機会を洗い出す)
気候変動がもたらすリスクと、対応を通じて得られる機会を明確にすることが必要です。
- リスクの例:
- 猛暑による作業員の熱中症リスク
- 電力料金の高騰による製造コストの増加
- 水害で工場が一時的に操業停止する可能性
- 機会の例:
- 空調設備の省エネ化によるコスト削減
- 太陽光発電設備導入による自家消費の促進
- 「環境に配慮した工場」としてのブランド価値向上
これらのリスクと機会を整理し、必要に応じて対応策を立案します。
6.2 品質目標及びそれを達成するための計画の策定
(気候変動への対応を品質目標に反映)
気候変動への対応を品質目標の中に組み込むことも検討します。例えば、「2025年までに工場内の照明をすべてLED化する」「エアコン使用電力量を前年より5%削減する」といった目標を設定し、エネルギー効率の向上を品質活動の一部として推進できます。
7.3 労働者の認識
(従業員に気候変動への意識を促す)
気候変動への対応は、経営層だけでなく現場従業員の理解と協力も必要です。省エネ運転の徹底、空調の適正使用、廃材の適切な処理など、日常業務の中での環境配慮を推進するために、社内掲示や朝礼での周知活動を行うことが有効です。
9.3 マネジメントレビュー
(気候変動の影響を定期的に評価・見直す)
マネジメントレビューにおいて、気候変動に関連する外部課題や利害関係者の要求事項、リスク・機会の見直しを行います。たとえば「前年に比べて夏場の電力使用量が増加した理由は何か」「新たな顧客から環境対応についての要求があったか」など、気候変動に関する実態とその対応状況を定期的に確認・改善します。
御社が今すぐできること
|
項目 |
取り組み例 |
|
外部課題 |
「異常気象による納期影響」「電力価格高騰」などを記録 |
|
利害関係者 |
顧客・自治体の省エネ要望をリストアップ |
|
リスクと機会 |
電力料金・暑さ対策などを分析し、対策案を検討 |
|
目標設定 |
「LED化率」「電力使用量削減目標」など数値で設定 |
|
教育・周知 |
朝礼や掲示板で「気候変動対応の取組」を共有 |
|
レビュー |
年1回、気候変動関連の進捗をマネジメントレビューで確認 |
このように、ISO 9001の枠組みに沿って、現場に即した形で気候変動への対応を組み込むことが可能です。
