ISO9001文書の作り方|現場で使える標準書・記録のコツ〜形だけで終わらせない、シンプルで実用的な文書の設計法〜03
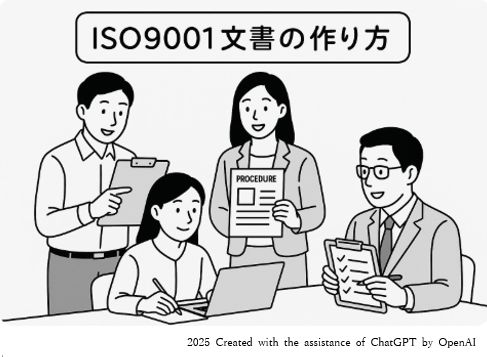
「ISOの文書、正直うちでは全然使われていません…」
ISO9001を導入したけれど、
- 「文書が多すぎて誰も読まない」
- 「現場の作業と合っていない」
- 「記録のための記録になっていて、面倒くさいだけ」
こんな声が聞こえてきませんか?
ISO文書は、“審査員に見せるための書類”ではなく、“現場が使って改善に活かすための道具”です。
この記事では、中小製造業でもシンプルかつ実用的に運用できる文書や記録の作り方を、具体例とともにご紹介します。
1. そもそも「ISO文書」って何を指すのか?
ISO9001では「文書化された情報」という表現が使われます。これには大きく分けて2種類あります。
- 📖 規定類・手順書(計画系)
→ どうするのか?というルール・決まりごと - 📝 記録類(結果系)
→ 実際にやったことを残す証拠、再発防止・改善の材料
たとえば「作業手順書」「教育記録」「クレーム対応記録」「品質目標管理表」などが該当します。
重要なのは、””分厚さや難しさではなく、“目的に合っているか”””です。
2. 中小企業でよくある“ISO文書の失敗例”
導入直後やコンサル任せで作ったISO文書には、次のような“あるある”な問題が見られます。
📌 ① テンプレートをそのまま使ってしまい、自社に合っていない
→ 大企業向けや他社のフォーマットをそのまま流用すると、
「実務に合わない」「項目が多すぎて現場が困惑」などの事態に。
📌 ② 専門用語だらけで、誰も読まない・覚えない
→ 「是正処置」「パフォーマンスの監視及び測定」など
→ 説明なしでは伝わらず、形だけの記録になりがち。
📌 ③ 記録が義務的な作業になり、“やらされ感”が強まる
→ 本来の目的を忘れ、「とりあえず埋める」記録になってしまう
→ 結果的に改善につながらない、意味がないものに…
3. “現場で使える文書”をつくる3つの考え方
✅ ① ISO用語より“現場の言葉”を使う
たとえば…
|
ISO用語 |
現場での言い換え例 |
|
是正処置 |
トラブルのあと、どうしたか? |
|
不適合 |
ミス・クレーム・不具合 |
|
パフォーマンスの監視 |
日常点検・数値の記録 |
|
教育訓練記録 |
説明しましたメモ、OJTチェック表 |
理解できる言葉で書くことで、社員が納得して動けるようになります。
✅ ② 業務の流れに沿って書く
「作業手順書」や「チェックリスト」は、実際の流れに即して書きましょう。
たとえば作業手順なら、
- ① 使う道具をそろえる
- ② セット位置を確認する(写真付き)
- ③ 操作手順を番号順に記載
- ④ チェック項目を○×で記録
- ⑤ 終了後の片づけと点検
→ 「読む」より「見てすぐわかる」設計が理想的です。
✅ ③ 記録は“必要最小限かつ活きる内容”に
記録が目的化してしまうと、形式ばかりで意味を持ちません。
記録の設計で大事なのは、「あとで見返して改善に使えるかどうか」。
たとえば、
- クレームの内容だけでなく「原因」と「対応の結果」まで簡潔に記録
- 社員教育では「何を伝えたか」「理解の有無」だけをシンプルにチェック
- 日常点検では、数値か○×で完結する欄を設ける
4. 実際に使われているおすすめフォーマット例
📄 標準作業手順書(SOP)
- A4横1枚
- タイトル/目的/使用機器
- 手順(写真・図入り)を3~5ステップにまとめる
- 最後に「チェック欄(○×)」「担当者名」「日付」
🗂 記録様式(チェックリスト型)
- 工程ごとに必要な確認項目を並べる
- ○×、数値、選択式などで記入負担を減らす
- 一覧で複数日記録できるような工夫も◎
📝 社内ルールや指針
- 「誰にでも伝わる言葉」で作成
- 漢字・専門用語を減らし、口語調や箇条書き中心に
- 運用しながら都度修正できる“たたき台”として使う
5. 文書を“形”で終わらせないための運用の工夫
👥 現場メンバーを巻き込む
作成・見直しの場に現場の人が関わることで、
“「自分たちで作った文書」→「使う意義がある文書」”に変わります。
🔄 つくったらすぐ試す(試運転→改善)
一度作った文書も、現場で実際に使ってみると課題が見えてきます。
- 「この表現、わかりづらい」
- 「チェック項目が多すぎて時間がかかる」
▶ 実運用を前提に、「完璧より改善しやすい文書づくり」を意識しましょう。
📢 見えるところに掲示・共有する
- 朝礼で読み合わせ
- 作業台近くにラミネートして掲示
- 教育時に使い回す
「自然に目に入る場所」にあることで、文書が生きた存在になります。
次に読むべき記事&おすすめ診断
ISO9001の文書は、審査対応のためだけに作るものではありません。
“誰のために、何のために使うのか”を明確にしたうえで、現場が活用できる形にすることがポイントです。
形式だけの書類にしないために、今回ご紹介した考え方やフォーマットをぜひ活用してください。
次回の記事では、ISOの導入を成功に導く「社員教育」についてお話しします。
現場を巻き込むには、ちょっとした工夫が大きな差を生みます。
📘 次に読むべき記事:
👉 《社員がついてこれるISO教育|中小企業の巻き込み方とは?》
📋 あわせて読みたい:
🔍 今のISOで満足ですか?プロが改善方向を提案する一日診断
▶一日診断)
“使える文書”が、ISOを現場に根づかせるカギ
ISO9001の文書は、審査に通るための“義務”ではなく、現場で活用され、改善につながる“道具”であるべきです。
用語や構成にこだわるよりも、「誰が読んでもわかる」「現場で使える」ことを第一に。
文書そのものを“育てる”という視点で、少しずつ運用に定着させていきましょう。
